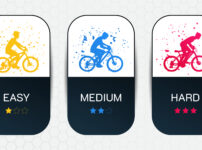こんな方におすすめ
- 月次決算の流れを知りたい!
- 月次決算をする意味ってなに?
- 月次決算を締めるにはどんなことが必要?
こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
この記事で紹介する「初心者が月次決算を締めるために知りたいこと」をご参考にすれば、
みなさんの経理ライフや転職活動の参考になりますよ!
経理未経験者で転職した筆者自身、初めての月次決算は非常に苦労しました。
最初は分からないことばかり。上手く周りに手伝ってもらうのが大切ですよ!
プライム企業の経理4年目、税理士試験に合格した現役経理マンが紹介します。

記事前半では「初心者が知りたい月次決算の具体的なスケジュール」について、
後半では「初心者が月次決算を締めるために知りたいこと」について解説するので、ぜひ参考にしてくださいね!
【初心者向け】そもそも月次決算って何?


そもそも月次決算ってなに?
会社に勤めていれば、経理でなくても月次決算って言葉は聞いたことがありますよね。
月次決算に関する内容を確認する前に、
まずは、『月次決算』の定義をしっかりと抑えておきましょう。
結論からいうと、月次決算とは、『その月の会社の成績を作成する』ことです。
そもそも『決算』=『会社の成績』のこと。
なので、『6月の月次決算』といわれたら、6月の会社の成績のことをいうわけです。
経理未経験者のみなさんも、
経理から『6月の経費の請求書はこの日までに出してください。』
というアナウンスを受け取ったことがあるかと。
これは、『経理が6月の成績を作成したいらから、情報ください!』
と言っているわけですね。
メモ
ちなみに、実務では決算を作成することをよく『決算を締める』って言い方をします。
これは、『決算が締まる』=『成績の集計が完了した』と意味すると覚えておきましょう!

そもそも毎月決算を締める必要ってあるの?
こんな疑問が浮かんでくるかたもいますよね。
経理以外の人からすると、会社の決算って1年に1回締めればいいって感覚がありますよね。
もちろん、毎月決算を締めなきゃいけない法律はありません。
とはいえ、1年に1回だけしか会社の成績を締めないのは不安でしかないのは、想像できるかと。
具体的には、月次決算をしないデメリットとして、
『経営者が会社が順調か?ヤバいか?をすぐに把握できない』
という問題があります。
そうなると、
いろいろな判断をするのが難しく、経営の判断が遅れて、競合他社に負ける原因にもなりますよね。
船長に潮の流れや天候の状況の情報が入ってこないと、間違いなく船は沈没しますよね。
なので、経営者にスピーディーに正確な情報を渡してあげるためにも、月次決算を締めることは大切なわけです。
ポイント
- 月次決算=その月の会社の成績のこと
- 月次決算に法律義務はないが、経営者に会社の状況をスピーディーに伝えるためにも月次決算は必要
初心者が知りたい月次決算の具体的なスケジュール

月次決算の定義を確認したところで、月次決算では具体的にどんな作業をするのか確認しましょう。
結論からいうと、以下のスケジュールです。
- 1~3営業日 売上、仕入、経費の計上
- 4~5営業日 減価償却・原価計算
- 6~7営業日 決算整理仕訳の計上
もちろん、会社の規模や業界によってそれぞれ違いがありますが、
この3つのフェーズに分解できるケースがほとんどかと。
それでは、1つずつ解説していきますね!
【月次決算・1~3営業日】 売上、仕入、経費の計上
最初のフェーズでは、売上、仕入、経費の計上を行います。
要するに、他部署から集まった情報を集計するわけですね。
そもそも経理の仕事は、他部署から情報を集めて決算を作成することが基本。
なぜなら、売上や仕入などの取引を実際に行っているのは経理ではありません。
例えば、
- 売上なら営業部門
- 仕入なら購買部門
といったように、それぞれの部署から数値のデータをもらう必要があるわけです。
経理は各部門から提出されたデータをもとに仕訳を計上していくわけですね。
他にも経費であれば、各部署の従業員から請求書を受け取ります。
みなさんも、
経理から『第3営業日までに資料を提出してください!』というメールを受け取ったことがあるかと思います。
しかも、期限通りに資料を提出しないと、経理からめっちゃ怒られますよね。
これは、期限通りに提出してもらわないと、スケジュール通りに経営陣への成績報告ができないからです。
メモ
会社の規模が大きくなると、各部署に仕訳を計上してもらうので、
経理は、集計データは正しいか?勘定科目は正しいか?などのチェック作業がメインになりますよ!
【月次決算・4~5営業日】 減価償却・原価計算
次のフェーズが、減価償却と原価計算です。
なぜ、このタイミングでこれらの処理をするかというと、
- 減価償却であれば、固定資産の取得
- 原価計算であれば、材料の購入
といったように、計算のもとになる仕訳が計上されてからじゃないとできない処理だからです。
要するに、減価償却費や原価計算の処理をするためには、1~3営業日で前処理が必要になるわけですね。
例えば、減価償却費の計算。
減価償却費の計算を1営業日に処理する。
⇓
新しく取得した固定資産の仕訳が、3営業日に計上される。
(他部署から請求書が3営業日に経理に回ってくる)
となると、新しく取得した固定資産の減価償却費の処理が漏れてしまいますよね。
このように、処理に漏れがないように、4営業日に設定されているわけです。
みんながバスに乗っていることを確認しないで出発してしまうと、
取り残された人を連れ戻すのに、無駄な時間が発生してしまいますよね。
つまり、効率よく計算することを考慮してスケジュール管理しています。
【月次決算・6~7営業日】 決算整理仕訳の計上
最後のフェーズが、決算整理仕訳の計上です。
具体的には、
- 前払・未払費用の処理
- 引当金の処理
などが挙げられます。
つまり、他部署の情報を入手して計上するのでなく、経理特有の処理とも言えます。
メモ
ちなみに最近では、新収益認識基準の適用がはじまったので、
- 売上の純額処理
- 売上から前受収益への振替
などを処理する会社もあるかと。
決算整理仕訳の計上が完了すると、その月の会社の成績が集計できたので、
いわゆる『決算が締まった』ことになるわけです。

月次決算が締まったら経理の役割は終わり?
もちろん、月次決算を締めることは経理の主な役割。
ですが、それ以上に重要なのが『数値の分析』や『経営陣への報告』です。
正直、月次決算を締めることは毎月行うルーティンなので、付加価値をつけることが難しいです。
要は、機械的な仕事なわけですね。
なので、経理として存在価値を見出すためにも、
- 予算に対して月次の成績が変動した要因はなにか?
- その要因は今後も続きそうか?
と分析的な思考で数値を確認することが必要です。
分析が完了したら、経営陣へ分かりやすく月次の成績を報告します。
注意したいことは、経営陣は経理のプロではないということ。
もちろん、経営陣は会社の業績を管理する責任があるので、ある程度財務諸表を理解できなければなりません。
とはいえ、経理の専門用語を並べてしまっては理解できませんよね。
なので、相手の知識レベルに立って報告する必要があるわけですね。
初心者が月次決算を締めるのに必要なこと


初心者が月次決算を締めるのに必要なことは?
月次決算の流れを確認したけど、実際に月次決算を締められるか不安な方も多いですよね。
では、月次決算初心者が決算を締めるのに必要なことはなんなのでしょうか?
結論からいうと、『分からないことは聞きまくること』です。
なぜなら、月次決算の期間って経理全体がかなり忙しい雰囲気になります。
そんな状況だと、『周りの人に聞きずらい』と思うのが普通の人間。
とはいえ、
- いくら簿記の勉強をして知識を身につけても
- いくら違う会社で経理の経験を積んでも
会社のオペレーションや会社の取引が違うので、
その会社の月次決算のルールは周りに聞かないと分かりません。
逆に、分からないことを自分で抱えてしまうと、
『業務が覚えられない』、『孤立感を覚える』という結果になってしまします。
大切なことは、『月次決算を最初から完璧にできることは不可能』と理解することです。

口では言うのは簡単だけど、なかなか周りには聞きづらい。。。
頭で分かってても、なかなか聞きづらいって方もいますよね。
事実、私がそうでした。
安心してください!
そんな方のために、以下の記事で経理担当者になる前に知っておきたいことをまとめています。
この記事の3つを意識するだけで、初めての月次決算を乗り越えるヒントになるので、ぜひ参考にしてみて下さい!
-

-
【技・体力・思考】経理担当者にチャレンジする人が知っておきたいこと3選!
まとめ
以上、月次決算初心者が実務をやるまえに知っておきたいことを解説しました!
経理未経験者にとって、月次決算は大変なことも多いのが事実。
ですが、慣れれば要領が分かってくるので、自分のペースで処理を進めることができますよ。
月次決算に初めてチャレンジするけど不安な方は、この記事を読み返して実践してみて下さい!
みなさんの経理ライフや転職活動の参考になれば幸いです。